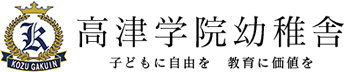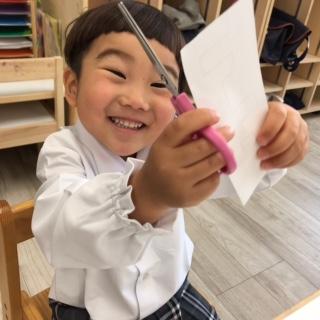2011.3.11
あの震災から10年。昨日多くのメディアでも取り上げられ、様々な特集が組まれていました。
1日経った今日。当たり前のようにメディアや当事者でない人々は日常が戻ったように感じました。
被災地の方々からすれば、10年でも、これまでも、これからも、復興を続けていかなければなりません。
当時私は小学校教員として子ども達と講堂で体育を行っておりました。
あの時の事ははっきりと覚えています。幼いころ阪神淡路大震災も経験しました。
大切なことは決して「忘れないこと」そして、毎日を一生懸命「生き抜くこと」。それらを子ども達と共に体現することだと考えます。
未曽有のコロナ禍、今後も様々な困難があれど、主体的に子ども達の未来が自らの手で明るくしていってくれること願います。
公園での出来事
今日、戸外遊びの公園で年少児が、「園長先生、松ぼっくりってどこに落ちてるん?」と聞いてきました。
私は、少し遠くの松の木を指差し、「あそこの松の木の下には落ちてるかもしれないね。」と答えました。
その子は嬉しそうに、その松の木に向かい私も追いかけ、松の木を見上げて、
「ほら、見てごらん、木の上に松ぼっくりがついてるでしょ。あれが落ちてくるんだよ。」
と伝え、その場は少し坂になっていたので、男の子が「坂になってるから、下に転がってるかも知れない。」と付近を探し始めました。
その後は私も児童看護があるのでその場を離れましたが、その後彼は4つ松ぼっくりを見つけ、2人の友だちに1つずつ、お母さんと自分に1つずつ持って帰ったのでした。
公園の松の木の松ぼっくりもかなり落ち切った後の様子でしたが、その子が遠くから私が指さした松の木を知っていたこと、松ぼっくりを知らぬ間にたくさん見つけていたこと、それを友だちにあげ、お土産も持っていたことに、1年以上経つ成長に日々に驚かされると共に、子どもの観察力の高さに感心させられた出来事でした。
音楽表現
12月20日(日)、この日は音楽表現の研修に行ってきました。
先生は、ピアノの堪能な方で幼児音楽に精通されている方だったのですが、大変わかりやすく指導してくださり、「音楽」に苦手意識のある人たちにとっても大変有意義なものであったと思います。
教師や保育士が大切なのは、ピアノや楽器を巧く演奏できるという技能ではなく、楽器は飽くまで「音楽」を楽しむ為のツールでしかなく、子ども達にまずは「リズム感」をつけてあげるということであるという事を学びました。
コードや和音の話までにもなったのですが、専門的な用語や技法についても非常にわかりやすく解説してくださいました。
思えば、幼稚園、保育園、小学校の先生は特に一昔前までは、「ピアノ演奏は必須」というような雰囲気でした。
しかしながらピアノをしていたほとんどの人たちはあまり幼少期に楽しくピアノに通ったという記憶はなかったようです。
(この研修に来られてたほとんどの方がそうでした。)
小学校でも、大きな行事の度に誰がピアノ伴奏するのかという、ある意味不毛な議論が延々となされていたことを思い出します。
この学びをしっかりと園にフィードバックして、子ども達と「音楽」を楽しみたいと思います。
学び
先週の土曜日、日曜日と保育・幼児教育に関する研修を受けてきました。
座学からソーシャルディスタンス、マスクファイスシールドをつけてのグループディスカッション。
たくさんの学びを見つけました。
立場上どうしても講師の先生側に目線が行ってしまうのですが。1日約8時間、都合16時間の研修を手を変え品を変え、プログラム我々に提供してくれることに感謝し、また、現場にフィードバックしていきたいと思います。
今回は一般的な保育や教育に関する研修でした。
モンテッソーリ教育と日本の教育の保育と共通性。それは保育者、教育者が子ども達の健やかな成長を願うものであるという事であると確認することが出来ました。
進化する園舎の為に今後も「初心」と「学び」を忘れずに常にアップデートしていきたいと思います。
出来事
今日は2つの嬉しい出来事がありました。
1つ目は、体験の時にお母さんが恋しくて泣いてしまっていた男の子がいたのですが、その前に体験していた今は入園している女の子がその子の為にいつも涙を拭くためのティッシュを持って来てくれていました。
自分もその気持ちがわかるのでしょうか。その男の子が泣くたびにその子はティッシュを持って来てくれていたのです。
その男の子も入園し、今では泣くこともほとんどなくなり、子どもの「自立」には驚かされるばかりなのですが、今日はそのずっとティッシュを持って来てくれていた女の子が泣いていたのです。その時その男の子がすっと来て、女の子にティッシュを持って来てくれました。
些細なことでありますが、2歳半をすぎたばかりのまだ1語文か2語文同士の子ども優しさにとても嬉しく、感心した出来事の1つです。
もう1つは異年齢から。
3歳の女の子がお迎えの間際に折り紙の飛行機を創り始めると、やはりお迎えが来られたので、「明日続きしようか。」と声をかけたところ、今作りたかったのか、泣きそうになってしましました。
すると、1つ年上の女の子が、
「○○ちゃんがチャチャっと飛行機折ってあげようか?」と声をかけ、すぐに本当にチャチャっと飛行機を折ってくれ、泣きそうになっていたその女の子は泣き止み、笑顔で降園していきました。
どちらもの出来事も子ども達の力と行動にまた驚かされると共に嬉しい出来事の2つでありました。
我々にできること
近頃、急に気温が下がり寒さも増してきました。予定していた懇談会も中止とせざるを得なくなり、少し沈んていた中でも、保護者の皆さまは毎日子ども達を送迎し、どんなに寒くても(暑くても)きちんと時間を守って下さりながら、園舎に子ども達を任せて預けていってくれます。
様々な我々園舎の方針(今回の懇談会の予定もそうでしたが)も理解してくださり協力してくださいます。
当園の園児はご近所だけでなく、自転車やお車、電車バスを使って登園してくださる方も少なくありません。
毎日の送迎は大変ですが、逆にその時間を大切な思い出として捉えられてる方もおられます。
子どもが少しでも体調が悪そうであれば、園の為に大事を取って休みますやこちらから熱がなくても少しでも体調が悪そうにしていればご連絡をするとすぐにお迎えに来てくださいます。そして我々に足りなかったこともきちんと説明しながら指摘してくださいます。
当然の事と言われてしまえばそうかもしれないですが、我々はそう簡単なことでは無いと考えています。雨の日の自転車の送迎や秩序の敏感期を区変えた子ども達の浮き沈みは本当に大変ですし、急遽の予定変更は少なからず、ストレスになります。
入園式の時に出席してくれたモンテッソーリ教師が「いつもここにくると、高津学院は保護者の方も高津学院を応援してくれているようですね。先生の願う”平和教育”は実現できるのではないでしょうか。」という言葉を貰いました。この言葉を大切にしております。
私たちが出来ることは、保護者の皆さまに安心してもらえうよう責任をもってお預かりすること、そして常に勤勉で内省的であること。準備を怠らず環境を整えること。子どもの人格が認められ、満たされた環境であり子ども自らの成長の手助けをしていくこと。それらを楽しみながらできれば最高だと思っています。
大人である私たちがいつも笑顔であれば、子ども達も笑顔になってくれると信じています。
今後も常に高津学院幼稚舎は最高の園を目指してアップデートし続け、子ども達と保護者の皆さま、教師と共に高津学院幼稚舎をより皆にとって安心でき、満たされる場所に創り上げていきたいと考えています。
その他の記事...