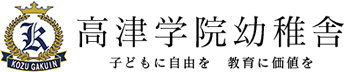書くこと
大人にとって"書く"という行為は簡単ですが、実は手首や指先のコントロールをたくさん必要とします。
だからこそ、子どもたちは自分で描くものを選び、"チョット難しい"に挑戦することを楽しみながら日々、積み重ねています。
同じような成長の階段をそれぞれが登っていますが、一人ひとりの階段の高さは違います。時には教師の予想を上回る成長があり、もうこんなに細かく書けるようになったのね!と驚かされることもあります。
もっと上手に書きたい!細かい違いを知りたい!と願う一人ひとりの敏感期を逃さないよう、子どもたちをしっかりと見て、これからも環境を整えていきたいと思います。
7月1日(土)モンテッソーリ教育講演会は以下より!!
↓ ↓ ↓
お話会
先週金曜日は、当園保護者の皆様とのお話会を開催いたしました。
モンテッソーリ教師から「人間の傾向性」についてのお話。そして園舎代表からは「発達の4段階」についてお話させて頂きました。
モンテッソーリが考えた様々な理論。私たちが学んだことを少しでも共有し、この自然科学的教育法が人間の発達や傾向性からなるものである。
決して早期教育や英才教育ということでは無い、生活教育、平和教育であるということについて共に考えさせて頂く良い機会となりました。

講演会は園舎の保護者の方のみならず、全ての「子ども達の成長を真剣に考える皆様」へのお届けです。
是非、お申込みください!!
7月1日(土)モンテッソーリ教育講演会は以下より!!
↓ ↓ ↓
創造性
"子どもの創造性を育みたい"
"発想力が豊かで、オリジナリティを持った子どもになって欲しい"
という思いは子どもの幸せを願う中で、自然と生まれてくるものと思います。
そんな力を子どもが持つ為にはまず、
「人の真似をすること」がとても大切です。
画家を目指す美大生も、初めは必ず優れた古典的な名作の模写を課せられるといいます。
楽器を習うにも、先生と同じ弾き方を真似することからのスタートです。
どんな分野でも優れたものを見て、それを真似することから、創造性は始まります。
子どもたちも今、周りで話している言葉、描いている絵、作っている作品、文字の書き方、身体の動かし方、他者への接し方を
一生懸命に見て、真似て、実際に自分の技術になるように、と練習を繰り返して吸収しています。
子どものオリジナリティを求めて「また真似っこばかり…」と捉えず、どんどん真似をして先人の築いてきた技術を習得した上で、それぞれの創造性が築けるように、正しい手本を見せた上で、真似る機会をしっかりと準備していきたいな、と思います。
モンテッソーリ教育講演会のお申し込みは以下から!!
↓ ↓ ↓
見通し
園舎の環境の中にはホワイトボードに「○じ ○○をします」と予定を書いて、時計の近くに掛けています。
字が読める子どもを中心に、登園するとボードを読んで今日の予定を確認しています。
昨日は10時に年長さんのお集まりがありました。時間までに片付けを済ませて集まった子もいれば、てっぺんに針がきてから片付け始める子もいました。遅れた子はみんなが集まっていることに気づいて急いでくれましたし、参加する際は自分から「お待たせしてごめんね」と言えたので、とても大切な気付きがあったと思います。次回にコッソリ期待しています。
時計に興味を持って、いま何時?とちらちら見てくれる姿も増えました。
先を見通す力にも繋がるといいなと思っています。
モンテッソーリ教育講演会のお申し込みは以下から!!
↓ ↓ ↓
休み明け
お休み明けの今日も、いつもと変わらず子どもたちは笑顔で登園してくれました。
後戻りすることなく、4月からの子ども達の成長は進むばかりです。
年長さんは自分の気持ちを柔らかく伝え、相手を待ってあげる余裕を自然と見せてくれるようになりました。
年中さんは自分の力で想いをカタチにすることが出来るようなっています。
年少さんは、やってみよう!という気持ちを沢山持って挑戦し続けてくれています。
そしてプレさんはそんなお兄さんお姉さんの背中を見て、仲間に入ろうと一生懸命です。
お休みの日に起きたたくさんの出来事を子どもたちに聞かせてもらい、よかったね!嬉しかったね!と、教師の心もぽかぽか幸せになった1日でした。
モンテッソーリ教育講演会のお申し込みは以下から!!
↓ ↓ ↓
その他の記事...