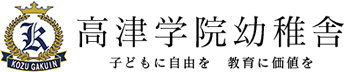間違い
私たちモンテッソーリ教師は、子どもたちが間違っていても "訂正しません" 。
子どもは否定されると心を閉ざしてしまうからです。
しかし、間違っていることを間違ったまま放っておく訳でもありません。
その場で「違うよ、こうだよ」と言う代わりにまずは、間違っているなぁ…という事実を頭の片隅に留めておきます。
そして、日にちや時間を変えて全く関係のないタイミングで伝え直すのです。
例えば数字をスラスラと書ける子がいて、
でもその書き順やバランスが間違っているとき。
楽しそうに書いている時は、間違っていても静かに見守ります。
そして次の日「一緒に数字の書き順を紹介したいんだけど…やってみる?」などと誘い、改めて紹介し直します。
すると子どもは否定されることもなく、
「ああ。こうやって書くんだった」
と、自分の中で間違っていた部分と照らし合わせながら自己訂正をしていきます。
子どもを否定することなく
「教えながら教えなさい」
とマリア・モンテッソーリは言いました。
子どものできた!を奪わずに、正しいことを伝えられる方法は、子どもを尊重する上でもとても大切にしたいものです。
教えてもらうこと
今日も一日、集中した子どもたちの顔が印象的でした。
おしごとに誘うと、やりたい!やってみる!ととても意欲的な子どもたち。
こちらも誘うのが楽しくなってしまいます。
以前は少し難しいと「やめとこうかな」「もうやめる…」と言う子どもたちもチラホラいました。
しかし日々の小さな自信の積み重ねから、挑戦する気持ちが芽生えたり、少し踏ん張る力が生まれてきたようです。
どの子どもにも、やってみたい!に繋がる日は必ずきます。
スキルや知能のレベルだけでなく、子どもたちの心の成長を見ながら、誘うおしごとを選ぶのも教師の役割だと思っています。
その為にも子どもたちと目を見て沢山お喋りをして、心を寄せて、今どんなことをどんな風に捉えて考えて過ごしているのか、一人ひとりから日々教えてもらっているのです。
子どもたちの活動
子どもたちの活動は、大人の想像を超えた発展や楽しさがあります。
毎日同じことのようですが、毎日違います。
今日は園舎内で焼肉屋さんがオープンしました。
手作りの焼き網、お皿、コップ、トング。何が必要かを友だちと相談し、役割分担をして進めていきます。
お店の人もお客さんもみんなが笑顔でした。
人気がありすぎて、お客さんはお店の外で待っています。お店の人はお客さんが並んで待てるように、誘導までしていました。
そこには、小さな社会ができていました。
毎日使っているチラシが、素敵な活動に発展していきます。
全ては、日々の積み重ねがあるからこその発展です。
毎日の活動を、見守っていきたいですね。
連鎖
子どもたちは毎日自分の時間を過ごしますが、同時に周りの子がやっている活動にはアンテナを張っています。
今日は数の引き算のおしごとを、年長さん3人がやりたい!と始めました。
するとそれを遠くから見ていた子たちがスーッと近づいてきて、ほかの数の活動を選び、近くに座って取り組んでいました。
あれはまだ僕には早い、と分かっているようでしたが、いつか出来るようになることも、分かっています。
一歩先だけでなく三歩先が見えているのは、縦割り保育の一つの特徴でもあります。
そしていつか憧れのお兄さんお姉さんがやっていた教具をさわる日がくると、子ども達はやっと私・僕の番!!!と目をキラキラさせるのです。
少し難しく
簡単なことよりも、むしろ少し困難なことの方が子ども達には人気があります。
以前は塗り絵のマンダラ模様が人気でした。
細かく色を塗り分けることも、パターンを考えながら塗ることも、新鮮で少し難しかったからです。
簡単になってくると、より難しいものや 手応えのあるものを求め始めます。
そんな子ども達に、今回はステンシルの活動を用意してみました。
色鉛筆でザーッと塗り込んでいたところを、絵の具を付けた小さなスポンジで叩くように塗り分けていきます。
見た目以上の忍耐が必要で、子ども達にもやり込む要素があります。
今日は年長さんが次から次へと手を伸ばしていました。
きっとチラチラ見ていた年下のお友達も、その内に挑戦してくれるのでは…と楽しみにしています。
愛情
高津学院の子ども達は、愛に溢れています。惜しみなく、大好きだよと伝えてくれます。
顔を見て、寄ってきて、全力でハグをしてくれます。
人として、これほど大切なことはないと思っています。
きっと生まれた時から、家族にたくさん愛情を注いでもらってきたのでしょう。
この幼児期に無条件に愛され、人を愛する心を持っている子ども達は、大人になってからも愛を分け与えてあげられる人になると信じています。
愛情に注ぎすぎはありません。
目を見て話を聴いてあげること、
相手の意見を否定しないこと、
大好きだよと伝えてハグすること。
私達も、どれも大切にしたいな、と思います。
その他の記事...