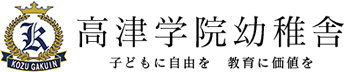将棋界
将棋界では史上初めて、藤井聡太棋士が日本の全タイトルを獲得しました。
日本におけるモンテッソーリ教育も藤井聡太棋士が受けた教育として一気に知名度が上がった事は言うまでもありません。
それ以外にも海外では、
Amazonの創始者 ジェフ・ペゾフ
Googleの創始者 ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリン
マイクロソフト創始者 ビル・ゲイツ
アメリカ合衆国元大統領 バラク・オバマ
アンネの日記の著書 アンネ・フランク
がモンテッソーリ教育を受けた著名人として周知となっております。
私は彼らの社会的な成功というよりも、共通点として、
・新しいことや挑戦に臆することがない。
・お金や地位や名誉ではなく、自分がどう生きるのか
・突き詰めていった先が誰もなし得なかったことに過ぎない
という所にあると考えています。
園舎の子ども達を見ていると、自分で決めて行動することは当たり前の事で、おしごとや製作に没入すると誰に言われずとも1.2時間はずっと座って何かに集中してる姿が見られるます。
幼い頃からこのような日常が習慣となり、大人になっていっても、自らの目標を設定し、それを達成していくことに喜びを感じながらも、社会や他者との尊敬や協力を惜しむことはない。
高津の子らに私は社会的な成功を願ったり、彼らのように有名人になってもらいたいとは考えておりません。
しかしながら彼らと同様様々な困難に打ち勝ちながらも、自分の人生を大切に、そして「主体的」に過ごして欲しいとそう切に願っております。
いよいよ明日に控えました元京都モンテッソーリ教師養成コース、コース長の岡山眞理子先生をお招きして対面での講演会。
こちらの講演会は大阪市天王寺区のご後援を受けどなたでもご参加いただけますので、是非ぜひ、皆様ご参加ください!!まだお申込み可能です!
↓ ↓ ↓ ↓
絵本の世界
秋‥実りの秋ですね。
公園では銀杏の実がたくさん落ちることから、その実りを感じることができます。
また、絵本では、今日は「いもほりバス」を紹介し、実りの秋を感じでいました。
この絵本はバスシリーズの1冊で、これまでに「いただきバス」「たなばたバス」「おつきみバス」と紹介してきました。
子どもたちの中には、以前に読んだのと同じだと気付いた子もいました。
この絵本の興味を引くところは、「バス」の言葉遊びがあるところです。
年長児は、その面白さに気付き、じっくり楽しむことができます。自分で言葉遊びをすることもできます。
年中児は、言葉のリズムを楽しみます。
年少児は、お話を楽しみます。
同じ絵本でも、吸収するポイントは違います。なので、絵本は同じものを何度読んでも、楽しむことができます。その日によって感じ方が違います。
季節の絵本ですので、来年はどのような気持ちで出会うのか、楽しみです。
10月14日(土)10:30から元京都モンテッソーリ教師養成コース、コース長の岡山眞理子先生をお招きして対面での講演会が次週の土曜日に控えております。
こちらの講演会は大阪市天王寺区のご後援を受けどなたでもご参加いただけますので、是非ぜひ、皆様ご参加ください!!
↓ ↓ ↓ ↓
レジリエンス
子ども達が大きくなっていく中で必要となる力の一つに"レジリエンス"というものがあります。
復元力とも訳されるのですが、何かにつまずいたり転んだりした時に、自分でもう一度立って歩き始められる力のことです。
つまり困難を乗り越えたり、上手く回避する能力のことです。
このレジリエンスの低さが近年では社会問題にもなっています。社会にでた途端に心を病んでしまったり、中には命を絶ってしまう人も増えているそうです。この力を育てるには、小さな失敗、小さな苦労を積み重ねた経験がとても大切です。葛藤を通して得た自律や自己コントロール力、そして我慢の力がレジリエンスに直結しているからです。発達の一歩先の活動を毎日積み重ねている高津学院の子ども達。自分の欲求と日々葛藤しているのがわかります。この繰り返しによってレジリエンスは必ず強くなります。
自分で立ち直る力。これは子ども達が大きくなっていく中でも、大人になってからも支えになるはずです。
大人に出来ることは、
失敗を許容できる環境を整えることと、「やってみよう!」「きっとできるよ」などの前向きな姿勢をもてる言葉掛けと、やっぱりやっぱり"信じて待つこと"、ですね。
10月14日(土)10:30から元京都モンテッソーリ教師養成コース、コース長の岡山眞理子先生をお招きして対面での講演会が次週の土曜日に控えております。
こちらの講演会は大阪市天王寺区のご後援を受けどなたでもご参加いただけますので、是非ぜひ、皆様ご参加ください!!
↓ ↓ ↓ ↓
気品と礼儀
モンテッソーリ教育の分野の中の1つに「気品と礼儀」という項目があります。
「どうぞ」や「ありがとう」、「活動を見てもいいですか?」とことわる活動や刃物の受け渡しや挨拶など。
当然させられるような活動ではありません。
子ども達が家庭から社会への第一歩となる幼児期に「社会性の発達」を見据えた活動が、様々な間接的な目的に入っています。
子ども達は個人としての知性や集中力を自らの力で伸長させながら、社会生活への準備を着々と進めています。
10月14日(土)10:30から元京都モンテッソーリ教師養成コース、コース長の岡山眞理子先生をお招きして対面での講演会が次週の土曜日に控えております。
こちらの講演会は大阪市天王寺区のご後援を受けどなたでもご参加いただけますので、是非ぜひ、皆様ご参加ください!!
↓ ↓ ↓ ↓
同じこと
子どもたちは、毎日同じ活動を繰り返すことから始まります。
生活そのものの中に秩序があります。安心があります。安心の中に心が満たされて、新しいことへの光を見出します。
毎日同じ絵を描いている、折り紙で同じものを折っている、同じお仕事をしている。など、大人は「また同じことしてる‥。」「別のことすればいいのに」と思うかもしれません。しかし子どもにとっては、「この活動がやりたい!手を使いたい!」という心の叫びがあります。
安心してお仕事ができる環境づくりは、大人ができる大切な役割の一つです。
子どもの笑顔や育ちのために、子どもがやりたいことを理解して、今何がしたいのかを見極めて、見守っていきたいですね。
10月14日(土)10:30から元京都モンテッソーリ教師養成コース、コース長の岡山眞理子先生をお招きして対面での講演会が次週の土曜日に控えております。
こちらの講演会は大阪市天王寺区のご後援を受けどなたでもご参加いただけますので、是非ぜひ、皆様ご参加ください!!
お申込みのリンクも貼っておきますね。
↓ ↓ ↓ ↓
挑戦(チャレンジ)
子ども達と共に日々過ごす先生方、当園舎でも教師が新たな挑戦を続けております。
モンテッソーリ教育の研修会や学会の参加はもちろん、今回はアシスタントの先生が、全体で行う「朝の会」に主としてチャレンジしてくださいました。
園舎で朝の会を行っていただくことは初めてでしたが、先生の素直な気持ちと日々の関係性の中で、子ども達はしっかり参加してくれと滞りなく朝の会は進んでいきました。
新たなことに「挑戦」することは「勇気」が必要です。今日の先生も前日は眠れなかったようです。
でもそのようなことが教師にとってのステップアップとして何より大切なのだとも考えます。
当園は、遠方より登園して下さる方もおられ、朝早くから下の子を抱え、徒歩のみならず、電車やバス、お車でお越し頂いている方々も少なくありません。それだけに大切な宝物であるお子さまをお預かりしているという自覚を持ち、日々当園の先生方も「挑戦」を続けられてます。
私も先生方を見習い挑戦を続けたいと思います。先ずは直近の大阪市天王寺区のご後援を頂いておりますオンラインお話会。
資料を作成する中で、うまくいくかどうか不安な気持ちと共に、早く皆様と共有したい!お会いしたい!!という気持ちが沸き上がってきております。
今週土曜日の開催ですが、まだまだご参加いただけます。
是非ぜひ以下プラットフォームのリンクよりお申込みくださいませ。
↓ ↓ ↓
嬉しいご報告
先日、卒園児のお子様が小学校に入られての大変嬉しいエピソードを頂戴いたしました。
・入学してすぐの時に担任の先生から、「こんなにちゃんと人の話を聞ける子は3年生くらいでもみたことないです。ご家庭でどんな教育されているのですか。」といったような事を言ってもらいました。
高津では普通のことだったことが外だとそうではないのだな、と改めて感じました。
・1学期の通知表には下記のように書いていただいてました。
「相手の目を見て、姿勢を正して話が聞ける〇〇さんは、みんなのお手本です。」
また個人懇談の際の話では
~1年生祭りをするときの役割分担で飾り付けをするグループに入っていたみたですが、
みんなが好きなのをつくっていくと数のバランスが合わなくて足りない飾り付けがあったみたいなのですが、〇〇がそれに気づいて率先してその足りない飾りを黙々とつくっていたようです。それで先生がそのことを他の子たちに伝えたら〇〇ちゃんが頑張ってるなら自分もやるといってみんなで作り始めたそうです。みんなのお手本になるような存在です。とこの時にも言ってもらいました。
〇〇が先生や友人の話をちゃんと聞ける人になれていることをとても嬉しく思います。本当にありがとうございます。
幼稚舎での3年間、保護者の皆様のご協力の下、共にたくさんの時間と経験を経て、人の話を聞く事ができる事、他の人の為に自然と行動できる事、やはりそれは自分が「経験」した事からなるものなのだと彼女の自立と成長を本当に嬉しく思います。
もうすぐ休み明け!!
高津学院幼稚舎では、夏休み明けの新学期に向けての準備が着々と進んでおります。
休み明けから新たに入園予定の園児さんの準備。休み前、在園児さん達の「今」の観察から環境の整備。キャンプの反省や新企画の立案。
そして何より9月は新年度のお問い合わせの多くなる時期でもあります。
当園でも現在、定員間近とはなっておりますが、しっかりと体験や説明会の準備をしていきたいと思っております。
そして何よりモンテッソーリ教育本格実施園としての自覚を持ち、この夏の学会発表で得た知見を深め、研鑽を職員皆で続けていきたいと思います。
嬉しかったこと
キャンプ開け、サマースクール最終週となった今週。
私たちは変わらず子ども達との生活を続けております。
夏休みに入り、人数こそ少し少なくなりましたが、子ども達の主体的な活動は止まりません。
その中でもモンテッソーリである先生方は自らの研鑽の為に、キャンプの疲れ切った次の日においてもご自身でモンテッソーリの教育の研修を受けられ、昨日、今日とすぐに子ども達にフィードバックしてくれています。
また、ある先生は、少しお約束がまだわかりずらい2歳児さんに、戸外遊び前「○○くん、あと3つだよ。外に行くからね。」と声掛けをさせておられ、それをすっと聞き入れ守ってくれたことに、彼の成長に、喜びを感じておられました。
こんな大人に囲まれた子ども達は幸せであると思います。
私はどうでしょうか。20年も人生の先輩の方々がこのように日々子ども達と向き合われる中、挑戦と研鑽を続けたいと全国大会の発表を準備します。
大切な子ども達や保護者の皆様、先生方がいるということを忘れずに。
失敗から学ぶこと
人生を幸せに生きるには「間違えたっていい、失敗してもいい」と思えることも大切です。
他人の失敗はもちろん、自分の失敗を許し、受け止められる人になるには、間違う経験、失敗する経験がたくさん必要です。失敗の中には、どうすれば良いかという答えが必ずあるからです。
子どもたちは世の中の全てを学んでいる真っ最中。失敗したときこそ、この答えを探し出します。誰もが生まれ持った「自分でじぶんを育てる力」を発揮します。
失敗を自覚している子どもには、大人にどうしてこうなったんだ、と考えさせられたり咎められる必要は全くありません。何度もやり直すチャンスさえあればどんどん間違えなくなっていくものなのです。
人間は誰しも失敗するし、教師も間違えることはあります。
失敗しても大丈夫。なんだってやり直すことができる。壊れたものは直せばいい。ただ、次に失敗しないためにはどうすればいいのか、それを自身の経験と気付きから幼児期に知っている子どもたちは、生きる力が強いのだと思います。
その他の記事...