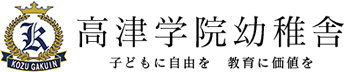観察力
子どもたちの観察力には毎日大変驚かされています。
大人なら流して見ていることも、子どもたちには連写のように写っているようです。
毎日出かけている東高津公園にはたくさんの草花があります。小さな花や、印象的にたくさん咲いている花など様々です。ですが、子どもたちはどこに咲いているかをよく知っています。
今日は、花を写真に撮って、クイズをしました。写真を見せて、どこに咲いているか探すクイズです。どの花もすぐにわかり、その場所へ走って行って確かめます。わずかな違いも見極めます。
子どもたちと探した花は15種類を超えました。
そんな自然豊かな公園で過ごすことができる毎日に、子どもたちと共に幸せを感じていました。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(7月現在5名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
自由
今日も子ども達の主体的な活動がスタートしました。
教室全体としての「観察」を行ってみると、子ども達はそれぞれに本当に自分のしたい事を「選択」しながら活動を進めています。
それらは友だちと共に行ったり、1人で集中したり。
年長さん達は図鑑を囲んで、何やら30分以上話しこんでいました。
そこにはやはり「自由」を与えられた子ども達のキラキラした姿がありました。
今日も子ども達の1日は光輝いているように自らの興味への探究に満たされておりました。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(7月現在5名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
お話会
先週の金曜日には、今年度、3回目となるお話会を行いました。
題材は「幼児期の子育ての重要性〜発達の4段階を手がかりに〜」です。
前半は子どもたちの普段の様子をお写真を添えてお話しさせていただき、後半はモンテッソーリ教育における「発達の4段階」を交えてお話ししながら、幼児期の日々の大切さを保護者の皆様と共に考えさせていただきました。
話をさせていただいてる最中も本当に「共同体感覚」に包まれ、共にやはり奮闘していきたい。そしてお預かりしている宝物である子どもたちの平和と自由を守り抜きたいと更に身の引き締まる思いでした。
質疑応答の際のはまさに「今。ここ」を子どもたちと過ごす保護者の方々の切実な思いが溢れ、本当に開催してよかったと思うことができました。
今後も保護者の皆様と子どもたちの成長を共に寄り添いながら見守り続けていきたいと思います。
自立と自律
子ども達の歩むは日々止まることなく留まることはありません。
プレさんから年長さんまでそれぞれがそれぞれのペースで「自立と自律」へのあゆみを確実に進めております。
それは、モンテッソーリ教育の子ども達の「自己教育力」の発見に伴う、環境を整える事を大切にした結果に他なりません。
教具へのアクセスのみならず、会話や生活そのものがモンテッソーリの理論に基づいております。
しかし、それは決して特別なものではありません。
子ども達のたくさんの心と体の成長に伴った科学的で論理的な集合となります。
年を重ねる度子ども達の充実と成長が溢れる高津学院幼稚舎は今日も子ども達の素敵な声が響いております。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(7月現在5名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
自然
自然は言葉がなくても、たくさんのことを私たちに教えてくれます。
毎日遊んでいる公園の草木、昆虫、鳥も同様です。
そして今園舎内では、アゲハの幼虫がその役目を果たしてくれています。
目の前で、絵本同様、それ以上の学びが展開されています。
一人ひとり感じ方は違いますが、その思いを大切にしてほしいです。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(7月現在5名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
継承
子どもたちは、無条件に小さい人に優しさをくれます。
そしてその優しさは、確実に次へと受け継がれていきます。
何気ない寄り添いや、そっと手を繋いだり、声掛けをする時に少しかがんだり。
その行いは学ぶというより、倣うが当てはまるように思います。
子どもたちのその素直な心が、笑顔で溢れる1日でした。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(7月現在5名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
ルール
グループで、ルールのある活動をすることがあります。
そんな時はまず、ルールの確認をします。
確認することで、内容を理解することができます。この時に、その日のアレンジもできます。子どもたちが出し合ったことを整理する時に、大人が少し手伝います。
自分たちで決めたルールですから、最後までやり切ります。
それが、室内のカードゲームだったり
戸外のボールあぞびだったり、場面は様々です。
ルールを守ろうとする心は、成長の証です。
社会性の敏感期と言えるのでしょう。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(7月現在5名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
週の始まり
今週も子どもたちの主体的な日々が始まりました。
細長い紙で三つ編みやジグザグ折を作る活動は、指先の微細運動が必要なお仕事です。
カラフルで好きな色でできることも魅力の一つです。
午前中をたっぷり使い、長く作ることができ、達成感を感じていた年長児さん。
長さを測ることにしました。
赤と青の数棒の1を、定規で測って10㎝確認後、どの数棒がぴったりかを合わせて、長さを確認しました。
明日も、長くなっていくのかもしれませんね。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(7月現在5名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
スキルアップ
年長児さんたちは、友だち同士で活動を作り出し、工夫して、毎日スキルアップをしているようです。
そんな時は、私たち大人が介入する隙はありません。それは会話であったり、活動の内容であったり、さまざまです。友だちのしていることを見て、さらにバージョンアップしたり、やりながら自分が満足いくように手直しをしたりしています。
お互いがいい影響を受け合っています。そして、友だちのしていることに、言葉を使って認めることもできます。
そんなお兄さん、お姉さんを見て、年下の子どもたちは倣います。
縦割りの素敵な姿ですね。
小さいお友だちに優しくし、大きいお友だちに憧れを持つ。そんな暖かい心が育つ毎日です。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(7月現在5名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
目標設定
今日も子どもたちは、自分の好きな活動に心を向けて取り組み、満足や達成感を感じる1日でした。
ある年長さんは、「◯◯までしたいから2枚ください。」と申し出てくれました。
目標を設定して、そこまでに何が必要かを考えることができていました。
とても素晴らしいと感じました。
目標を持って活動することで、より達成感もあるのではないでしょうか。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(6月現在5名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
その他の記事...