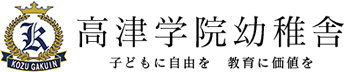達成感
子どもたちは日常の中でお仕事をしています。日常でも、その時によってお仕事をした感触は違うようです。
うまくいった、綺麗にできた、など。
今日は年少さんが、細い紙を交互に折っていくジグザグ折りをしていました。自分なりに納得いく仕上がりだったようで、素敵な笑顔で、見せにきてくれました。
今までにも何度も、何度も、挑戦したお仕事のはずです。でも今日の仕上がりはとても気持ち良かったようです。
このように、自分で活動して、満足できることで、自信となり、次への意欲へとつながるのではないでしょうか。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(5月現在5名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
自由選択
今日も子どもたちは、登園後すぐに自由選択活動に向かいました。
することを決めてきた子は、自分で場所を決めて始めます。
1人で集中したい時には、1人席をあえて選んでいます。
みんなに背を向けながら取り組む姿は、誰も声をかけることはできない雰囲気を放っていました。
一区切りすると、次は友だちと交流しながらグループ活動へと切り替えていました。
何をするか、どこでするか、誰とするか、全て自由選択の中で自分が決めることができる、そんな平和な空間でした。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(5月現在5名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
縦割りの良さ
縦割り活動の良さがこの時期顕著に出てきております。
それは、やはり年長さん達の「正常化」すなわち「自立」に他なりません。
徐々にこれまでにすでに終えている日常生活の練習分野に興味を示したり、新しく入園してきたプレさんのお世話をしたりと、自分以外の友だちに手を差し伸べる姿が多くの場面で見られます。
プレさんや年少さんが少し逸脱した行為をしているとしっかりと諭しながら注意してくれます。
「これをしたかったんだよね。うん。でもこれはこう使うんだよ。」
まさに訓練を受けた、モンテッソーリ教師のようです。
幼さもありなが小さな先生としてクラスの中で大活躍しております。
また、指先の洗練についてもご覧の通り。そこにはただ、縦割りにするだけではできない、年齢を経ることによってできるモンテッソーリの科学的な数理的な活動。日本の伝統文化である折り紙による論理的思考力の強化。決まらない規律や自由。そう生活そのものがモンテッソーリ教育の活動となるのです。
そんな前向きで、平和で、主体的な日々を子ども達は送ってくれております。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(5月現在5名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
始まり
1週間の始まり、今日もいつもの1日、かけがえのない1日。
子どもたちは、やりたいことに全力で取り組み、充実の1日でした。
ある子は、毎日欠かさない活動、ある子は先日友だちがしていたことで、やりたくなった活動など、きっかけは様々ですが、自由選択活動です。
きっと明日へと広がり、繋がる活動ですね。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(5月現在5名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
お話会
先週の金曜日にお話し会を行いました。
題材は「敏感気」と「大人の役割について」です。毎回自由参加にも関わらず多数の登園保護者の皆様に加え、体験に来ていただいた方や、入園前の保護者の方々にもご参加いただき賑わいを見せておりおります。会の後はご感想をいただいているのですが、本当に心温まるご感想をいただきそれを励みにまた今週も頑張ろうと決意の毎日です。
今後も気軽に参加できるようなお話し会を計画していこうと思います。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(5月現在5名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
習い事
習い事については、差し出がましい事を言って大変恐縮ですが、年長さんまでは「学習的」な習い事には注意が必要かもしれません。
というのは、幼児期の子ども達は「具体」から「抽象」への過程の最中であるからです。
マリア・モンテッソーリはこの過程を経てから、数字や文字といった抽象へのあゆみをとても大切にしました。
何でも「できるようになる」ことを目標とはしすぎないで、子ども達が楽しめる習い事を考えるのも1つの案かも知れませんね。
しかし、逆に年長から小学校に向けて子どもらの興味・関心の幅が広がっていく中で共に見学や体験をしながら様々な事に挑戦する姿勢はとても大切だと思います。
いずれにしても習い事は世の中に本当にたくさん溢れています。それらの本質を見ながらお子様と考えられてはいかがでしょうか?
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(4月現在4名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
お話
GWが終わり、子どもたちの元気な姿が昨日から戻ってきました!
昨日のブログにも書きましたが、久しぶりであることに、少し緊張していたかもしれませんが、それもあっという間に吹き飛び、いつもの空間の中に、変わりない様子が、当たり前のようにありました。
楽しかった経験を話す表情で、素敵なお休みだったことがよくわかりました。
たくさんの会話は、まさに言語のお仕事。
なんとか伝えようと、自分の語彙を目一杯使って表現していました。
今年も子どもたちが、自分で力を発揮できるように見守りながら、援助していきたいと思います。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(4月現在4名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
GW明け
連休明けの登園。早速それぞれの活動に取り組む子ども達。
高津学院幼稚舎の強みです。
整えられた環境の中で、また毎日主体的な日々を自ら、そして仲間と教師と。
大切に過ごしていきたいと思います。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(4月現在4名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
ハサミの使い方
子どもたちは、毎日自分のやりたいお仕事に向かいます。
同じお仕事に、じっくり取り組むこともよくあります。
その一つに、ハサミのお仕事があります。
最初はザクザク、線があるにも関わらず、とにかく切っていました。
何度も何度もすることで、どんどん上手になり、線の上を正確に切れるようになってきます。それを長く繋げたり、横に並べて王冠にしたりして楽しんでいます。
毎日やりたいからこそ、その扱いを丁寧にしてほしい、危険がないようにしてほしいと思っています。
時折朝の会でハサミの扱い方についてみんなで確認をします。
便利な道具だけど、使い方を間違えると、とても危険な道具になります。
子どもたちに扱い方を問うと、みんな大正解!全てはみんなを守るためのお話であり、方法です。
一緒に安全について話し合うことができました。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(4月現在4名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
小さな先生
縦割りの高津学院幼稚舎、子どもたちの縦のつながりが、毎日見られます。
先日、年少さん同士で、小さなトラブルがありました。1人が泣き出したことで、みんなが注目することになりました。すると、年長さんが、間に入り事情を聞き、双方に対して的確に関わってくれていました。
当事者の年少さんは、それぞれに納得することができ、活動へと戻ることができました。
その場面を、近くで見守っていた私たち教師は、その後年少さんに声を掛け、さらに小さな先生として、年長さんの成長を確信することができました。
高津学院幼稚舎では2025年度プレさん(2022年4月1日から2023年3月31日生まれのお子様)のご入園の募集を開始しております。
今年度は前後期制となっており前期(4、5、6、7、8、9月)後期(10、11、12、1、2、3)各月に1,2名の枠となっております。
各月枠が決まり次第締め切りとなります。定員は今年度も毎年同様、8〜10名の枠となっております。(4月現在4名のお申込みが決定しております。)
毎年度なるべく早くご体験いただくことをおすすめしております。
無料体験は2歳6ヶ月にお子様がなられてからお受付できます。
お子様の幼児期を大切に、モンテッソーリ教育を本格実施園に少しでも興味のある保護者様は是非1度体験もしくは見学、個別説明会に以下のフォームよりお申込みください。
※見学や個別説明会についてはお子様のご年齢は問いません。お子様がお生まれになられたすぐやご夫婦のみのかたも多数おられます!
お申し込みお待ちしております。
↓ ↓ ↓
その他の記事...